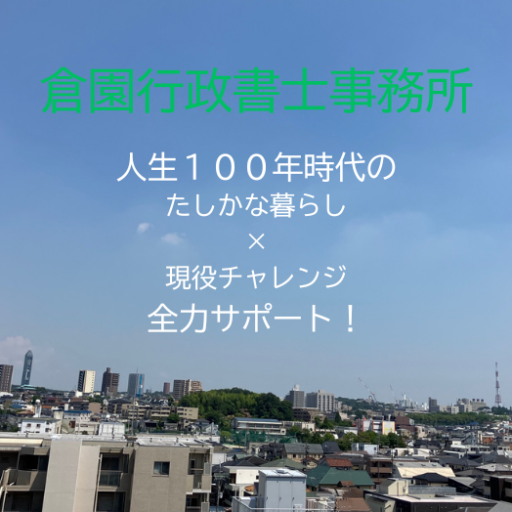建設業関連許可等
産業廃棄物収集運搬業許可
建築現場や解体工事では大量の廃材、コンクリート片、金属くず、石膏ボードなどの産業廃棄物が発生しますが、これらの処理責任は元請業者となります。こうした廃棄物の適切な運搬・処理を行う請け負い体制があることで元請業者からの信頼が得られ、業務の拡大にもつながります。
根拠法令:廃棄物処理法
- 目的は、廃棄物の排出の抑制と、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理、そして生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること
- 「廃棄物」は、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物で、固形状又は液状のものと定義され、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分される
- 「産業廃棄物」は事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物。中でも爆発性や毒性など人々の生活に危険を及ぼすものを「特別管理産業廃棄物」という。「産業廃棄物」以外の廃棄物が「一般廃棄物」となる。
許可概要:
産業廃棄物(事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥等)の収集又は運搬を業として行う場合、産業廃棄物の積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けることとなっています
許可要件:
- 産業廃棄物の収集運搬に関する講習を修了すること
- 産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
- 経理的基礎を有していること(経常利益等が0以上、債務超過でないなど)
- 事業計画を整えていること
- 欠格事由に該当しないこと
古物商許可
工事現場から排出される廃棄物のなかには、金属くず、廃プラスチック、紙類など、有価物化できるものもあります。廃棄物の処理責任がある元請業者にとって、収集運搬業者が古物商許可を所持していれば、廃棄物の中に有価物がある場合、新たな買い取り業者を探す手間をかけることなく、収集運搬費用と相殺できるなど、コスト抑制のメリットがあります。
また廃棄物量の削減にもつながり、環境保全の効果もあることから、環境やリサイクルへの目標を持っている企業は多くあり、古物商許可を持つ廃棄物業者への期待は大きいといえるでしょう。
根拠法令:古物営業法
- 目的は、古物の売買等には、その性質上、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があり、これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれが多分にあるため、法令等で定められた各種義務を果たることによって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していくこと
- 「古物」とは、一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたもの、これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたものをいう
許可概要:
古物営業を営もうとする場合は、都道府県公安委員会の許可を受けることとなっています
許可要件:
- 主たる営業所を設けること
- 営業所ごとに管理者を1名置くこと
- 欠格事由に該当しないこと
解体工事業者登録
解体工事業は老朽化した建築物の撤去など建設業界で需要は高く、この需要に応えることで、建設業法に基づき適切な手続きと基準を満たしていること、解体作業に関する専門知識と技術を有していることを示すことができ、元請業者の信頼を得ることができます。また元請業者にとって、工事の質や安全性を確保できること、建設業法に基づく指導や監督の負担を軽減できることなど、双方にとってメリットがあるといえます。
根拠法令:建設リサイクル法
- 目的は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図ること
登録概要:
解体工事業を営もうとする場合は、その請負金額の多寡や元請・下請けにかかわらず、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けることとなっています
(但し、土木工事業、建設工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた場合は不要)
許可要件:
- 工事現場における解体工事の施工の技術的管理を司る技術管理者を専任すること
(技術管理者:実務経験や資格等の主務省令に定める基準に適合すること) - 欠格要件に該当しないこと
浄化槽工事業登録
適用法令:浄化槽法
目的は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与すること
登録概要:
浄化槽工事は一般には比較的小規模であるため、これらの工事を行う浄化槽工事業者は建設業法の許可の対象から外れている場合があります。浄化槽工事を行う場合、当該工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けることとなっています
(但し、土木工事業、建設工事業又は管工事業に係る建設業の許可を受けた場合は届出で可)
登録要件:
- 営業所ごとに浄化槽設備士を置いていること(営業所の常駐・専任は求められず、複数営業所を担当することもできる)
- 欠格事由に該当しないこと
電気工事事業者登録
電気工事業は建築工事において不可欠な要素です。たとえば建築会社やリフォーム業者と提携することで、新築住宅やオフィスビルの電気設備設計・施工を提供し、建築プロセス全体の効率化を図ることができます。
また太陽光発電の設備設置では、再生可能エネルギー関連企業と連携し、専門知識を活かした持続可能なエネルギーソリューションを提供するなどなど、さまざまな分野での活躍が見込まれます。
適用法令:
電気工事士法
電気工事(一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備に限る。))の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与すること
電気工事業法
電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安の確保に資すること
登録概要:
一般用電気工作物等や自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする場合、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けることになっています
なお建設業許可を受けた業者は、電気工事業開始を届け出ることで、みなし登録電気工事業者となることができます。
- 都道府県知事:1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置
- 産業保安監督部長:2つ以上の都道府県かつ1つの産業保安監督部の区域内に営業所を設置
- 経済産業大臣:2つ以上の都道府県かつ2つの産業保安監督部にまたがる区域に営業所を設置
登録要件:
- 営業所ごとに主任電気工事士を置いていること
- 営業所ごとに電気工事に必要となる器具類を備え付けていること
報酬額
| 報酬額(税抜き) | 手数料 | |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 110,000円 | 81,000円 |
| 古物商許可 | 60,000円 | 19,000円 |
| 解体工事業者登録 | 60,000円 | 33,000円 |
| 浄化槽工事業登録 | 40,000円 | 35,000円 |
| 電気工事業者登録 | 50,000円 | 22,000円 |
| みなし登録電気工事業者届出 | 40,000円 |