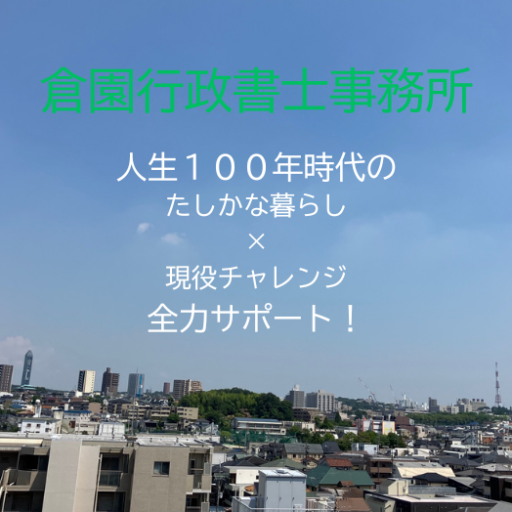起業や副業を始める際、個人事業主として活動をスタートすることもありますが、法人化することで社会的信用の向上や節税効果などのメリットがあります。
副業を始める方にも法人化は有効な選択肢です。副業を法人化することで、本業との分離が明確になり、収入や支出の管理がしやすくなります。
また個人事業主として活動を続けている方々にとって、事業規模の拡大や経営の安定化を目指す過程で「法人成り」を検討するタイミングが訪れることがあります。
法人成りとは、個人事業主としての事業形態を法人(株式会社や合同会社など)に変更するもので、事業の信頼性向上や資金調達の多様化、節税効果など、多くのメリットをもたらします。
そこで成功のカギとなるのは、業種ごとの特性や課題を理解し、適切な準備を行うことであり、専門家のアドバイスを活用しつつ、事業の将来像に合わせた法人化を検討が大変重要になります。
法人化
法人化のメリット
社会的信用の向上:
法人名義で契約や取引を行うことで、事業の信頼性が高まり、大口の取引先や金融機関との関係が構築しやすくなります。
事業拡大の可能性:
従業員の採用や新規事業への投資がしやすくなります。
節税効果:
経費として認められる範囲が増えるとともに、一定の所得を超える場合、法人税率適用により所得税の累進課税の影響を軽減できます。
責任の限定:
事業上の責任が法人に帰属するため、個人の財産が直接的なリスクにさらされることを防ぐことができます。
社会保険への加入:
社会保険への加入が義務付けられ、従業員の福利厚生が向上します。
法人化の留意点
コストがかかる:
法人設立には登録免許税などの費用が必要となります。また法人事業税・住民税等の納付義務や社会保険料の負担も発生します。
経営者の責任の変化:
法人化することにより、取締役としての法的責任も負うことになります。
また法人としての法的義務や税務申告等の複雑さが増すため、これらに対応するための知識や専門家のサポートが重要になります。
労務管理:
法人として従業員を雇用する場合、社会保険や労働基準法に基づく義務が発生することになるので、適切な労務管理体制の構築が求められます。
法人化の手続き
法人設立
定款の作成と認証
定款とは、法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などに関する基本的な規則のことで、必ず記載無ければならない絶対的記載事項、記載しなければ効力をもたない相対的記載事項、任意に定めることができる任意的記載事項があります。
絶対的記載事項には、目的、商号、本店所在地、資本金、発起人(氏名・名称、住所)、発行可能株式総数があります。
株式会社設立には、定款を作成後、公証役場で公証人の認証を受けることで、法律的な効果が発生します。
法人登記
公証人による定款認証を受けた後、法務局に対し、定款や法人の印鑑証明書、出資金の払込を証明する書面等とともに登記の申請を行うことで、法人設立の手続きは完了します。
会社設立後の各種手続き
社会保険
健康保険や厚生年金保険は年金事務所、雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)、労災保険は労働基準監督署にて手続きを行います。
税務関係
会社設立・青色申告の届出、源泉徴収等は税務署、法人事業税等は自治体にて手続きを行います。
業種の許認可関係
法人化に伴い新たに事業許可等を取得する、あるいは個人名義から法人名義への変更など、それぞれの許可行政庁にて手続きを行います。
取引先等との関係における変更手続き
取引先等との既存契約に係る法人名義への変更や法人用の銀行口座開設、加入している団体等への名義変更の届出など、必要な手続きを行います。
業種の許認可手続き
営業許可の申請は、要件や必要書類が多岐にわたり、初めての方にとっては複雑に感じられるかもしれませんが、当事務所は申請手続きのプロフェッショナルとして、皆さまに寄り添いながら、安心して申請を進められるように全力を尽くします。
また、事業開始後も、当事務所はお客様の伴走者としてサポートを続けます。事業運営においては、法律や規制の遵守が不可欠であり、事業者としての信頼を築くため、帳簿の作成や更新、定期的な許可の更新手続きなど、幅広いサポートにより適切な管理をご支援いたします。そして事業が成長し、法人化を検討される場合には、会社設立の手続きもお手伝いさせていただきます。
当事務所は、皆さまの挑戦を応援し、共に未来を築くパートナーとして、いつでもお力になります。
なお当事務所では主に以下の許可等を取り扱っていますが、これら以外の許可等についても信頼できる他専門家と連携してご支援いたします。
古物商
中古品を仕入れ、販売する事業を行う際には、古物商許可が必要となります。この許可は、盗品や不正取引を防ぐために、事業者が警察署の管理下で適法に営業を行うことを保証するものです。許可を取得するためには、成年であること、犯罪歴がないこと、適法な営業所を確保していることが必要です。また申請から許可取得までは約40日程度かかるため、事業開始の計画には余裕を持つことが大切です。
許可取得後は、営業所の変更や代表者の変更など、事業に関する重要な事項については速やかに届出や、取引記録を古物台帳に記載などが求められます。
当事務所では、事業者様が安心して営業に専念できるよう、申請書類の作成・提出だけでなく、事業開始後の台帳管理や手続き等ついてもご支援いたします。
許可要件や申請手続きなど、詳しくはコチラからご確認ください。

酒類販売業

酒類を販売する事業には、酒類販売業免許が必要となります。飲食店での提供や小売店、オンライン販売を行う場合にも適用されます。この免許は、事業者が適切に税務申告を行い、酒税法を遵守していることを保証するものです。取得には、安定した事業計画と適切な保管設備が必要で、審査には2〜3ヶ月程度かかります。
免許取得後も、仕入れや販売に関する記帳や年度ごとの販売量や在庫量等の報告義務があります。
当事務所では、さまざまな手続きの支援を通じて、事業者様がスムーズな運営が続けられるよう、支援いたします。
免許要件や申請手続きなど、詳しくはコチラからご確認ください。
旅行業
旅行の企画や手配を行う事業では、旅行業登録が必要となります。この登録は、旅行業法に基づき、事業者の信頼性を確保し、顧客を保護する目的があり、保証金の積立や旅行業務取扱管理者の配置が求められます。
登録後も契約内容の明確化やトラブル防止のためのガイドライン整備等の対応、登録内容変更時の届出などが求められます。
当事務所では、事業者様が信頼性の高い旅行サービスを提供できるよう、登録に必要な書類作成や保証金積立手続き等を支援いたします。
登録要件や申請手続きなど、詳しくはコチラからご確認ください。

宅地建物取引業
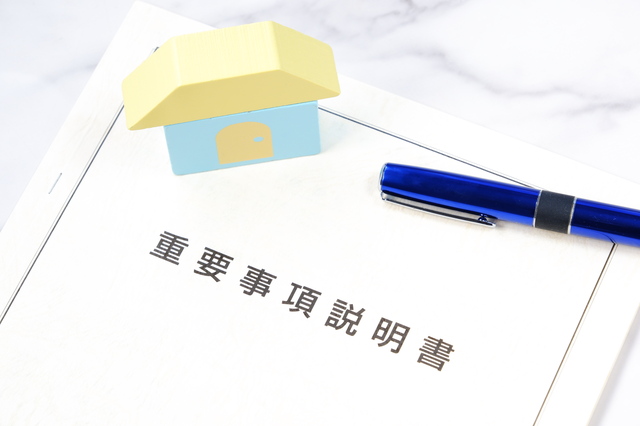
不動産の売買や賃貸の仲介など、不動産取引は顧客にとって人生の大きな選択となるため、事業者には高い信頼性と法令遵守が求められます。宅地建物取引業免許を取得するためには、事業所が法令で定められた基準を満たしていることや、取引士が一定数配置されていることが必要であり、この免許を取得することで、適法に事業を運営し、顧客からの信頼を得ることができます。また、宅地建物取引士は、重要事項説明や契約締結時の法的確認を行う、不動産取引において欠かせない役割を果たしています。
また免許取得後も、事業所の移転や役員の変更時の届出、取引にかかる重要事項の説明や帳簿の記帳など、事業運営には継続的な法令遵守が求められます。
不動産業は法的な責任が重く、顧客からの信頼が事業成功の鍵となります。当事務所では、事業者様が顧客からの信頼を築くことができるよう、宅地建物取引業免許の申請手続きや宅地建物取引士登録、免許取得後の各種サポートを通じて、不動産業の円滑な立ち上げと、適法かつ円滑な事業運営の実現を支援いたします。
免許要件や申請手続きなど、詳しくはコチラからご確認ください。
報酬表
| 報酬額(税抜き) | 手数料・登録免許税 | |
| 法人設立支援(※) | 60,000円 | 定款認証費用 50,000円(上限) |
| 古物商許可 | 60,000円 | 19,000円 |
| 酒類販売業免許 | 150,000円 | 30,000円 |
| 旅行業登録 | 120,000円 | 19,000円 |
| 宅地建物取引業免許 | 100,000円 | 33,000円 |
| 宅地建物取引士登録 | 30,000円 | 37,000円 |
(※)登記に関する司法書士報酬 及び 登録免許税(150,000円 下限)が別途かかります