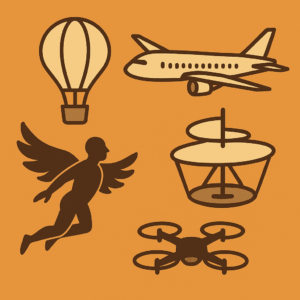第2回:大西洋から宇宙、そして空飛ぶクルマへ──常識を超えた挑戦の系譜
■ はじめに:空を飛ぶという“前例のない”挑戦
世の中の革新は、多くの場合、当時の常識や前例を超えるところから始まります。
空を飛ぶことも、その一つ。
有人飛行機、ジェット機、宇宙船、そして現代の“空飛ぶクルマ”と呼ばれるエアモビリティまで──いずれも、当初は実現性に疑問を持たれることも少なくありませんでした。
それでも挑戦し、実現した人々が、技術と社会を前に進めてきたのです。
今回は、常識を超えて飛び立った挑戦者たちと、その軌跡がもたらした変化をたどります。
■ 単独で空を渡った男:チャールズ・リンドバーグ
1927年、アメリカのパイロット、チャールズ・リンドバーグは、世界で初めてニューヨークからパリまでの単独・無着陸大西洋横断飛行に成功しました。
全長約5,800キロ、33時間半に及ぶ飛行は、当時としてはきわめて大胆な挑戦でした。
その成功は世界中の注目を集め、航空の信頼性を高めるとともに、航空路線の拡大や航空会社設立、関連技術への投資を一気に加速させました。個人の冒険が産業の未来を切り拓いた象徴的な事例です。
■ ジェットエンジンと音速への挑戦
第二次世界大戦後、飛行機はさらに“速く、高く、遠く”を目指します。
ジェットエンジンの実用化は、推力と燃焼効率を飛躍的に高め、それまでのプロペラ機とは桁違いの速度を可能にしました。
1947年には、アメリカ空軍のテストパイロット、チャック・イェーガーが、ベルX-1で、史上初めて音速(マッハ1)を突破。人類はこのとき初めて“音の壁”を越えたのです。
ジェット旅客機の登場は、国際交通を根底から変え、都市と都市の距離感そのものを再定義しました。
■ 宇宙へ:月面着陸とスペースシャトル
空を飛ぶというテーマは、しばしば当時の技術や社会の限界に挑むものでした。
1969年、アポロ11号によって人類が初めて月面に到達したのは、その象徴的な瞬間です。
その後のスペースシャトル計画では、「宇宙船を再利用する」という新しい発想が導入されました。
軌道船や固体ロケットブースターを海上で回収し、再使用する仕組みです。ただし、海水に浸かったブースターは分解・洗浄・部品交換といった大掛かりな整備が必要で、コスト削減効果は限定的でした。
それでも、宇宙輸送を単発の任務ではなく、継続的な運用に近づけたという意味で、大きな一歩となりました。
■ スペースXと民間ロケット再利用
21世紀に入り、アメリカのスペースX社(創業者:イーロン・マスク)は、液体燃料の第1段ブースターを打ち上げ後にエンジン逆噴射で減速し、陸上や洋上の着陸船に垂直着陸させる技術を実用化しました。
海水に触れないため整備負担が小さく、同じ機体を短期間で繰り返し飛行させることが可能です。
この方式は、ロケット運用の整備コストと打ち上げ間隔の常識を大きく塗り替え、高頻度かつ持続的な宇宙輸送を現実のものとしました。
■ eVTOLと“空飛ぶクルマ”という現代の挑戦
近年注目されているのが、eVTOL(電動垂直離着陸機)をベースとした「空飛ぶクルマ」構想です。
都市型エアモビリティ(Urban Air Mobility:UAM)とも呼ばれ、騒音が少なく、自動運転・電動化を前提に開発が進められています。
日本ではSkyDriveなどが商業運航を目指し、2020年代後半の実用化計画を掲げています。
これは、「渋滞を空で回避する」「高齢者や地方でも移動しやすい社会」を実現するための新たな挑戦でもあります。
■ 技術と社会が交わる場所に挑戦がある
歴史を振り返ると、空を飛ぶための技術革新の多くは、登場当初は前例が少なく、実現性も未知数でした。
それでも、その挑戦が物流・移動・生活圏・雇用・環境といった社会の在り方まで変えてきました。空を飛ぶことは、文明の設計図を更新し続ける行為なのかもしれません。
■ おわりに:挑戦のバトンを未来へ
空を飛ぶ技術に取り組んだ人々は、“飛ぶ”ことだけでなく“社会を変える”ことをも実現しました。
これから私たちが関わる空のものづくりや制度設計も、そのバトンの延長線上にあります。
挑戦が、社会と産業を動かす力になる──その事実を、あらためて心に刻みたいと思います。